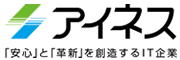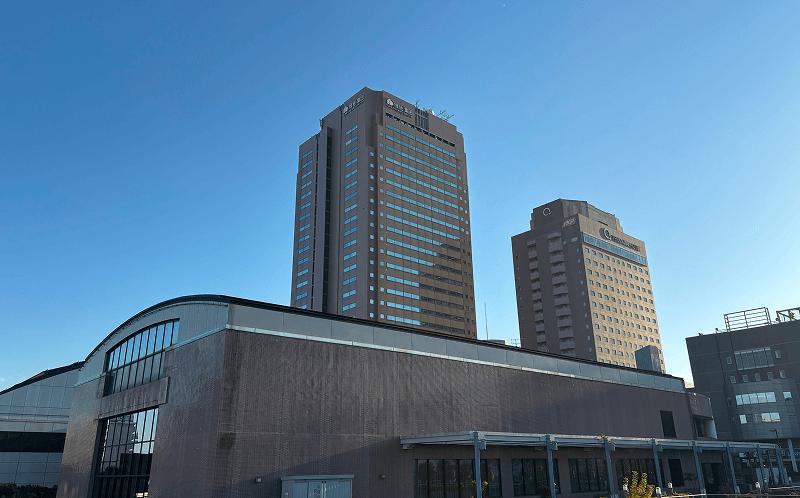【新潟県長岡市様】生成AIの要約機能がついた「AI相談パートナー」で、相談業務の負担を心理的にも時間的にも軽減


(左から)長岡市 行政DX推進課 行政DX担当係長 栗山 潤様、健康増進課 保健師 上石 寧々様、廣井 ゆい様
新潟県長岡市は、人口約25万5,000人で、米どころ、酒どころ、長岡まつり大花火大会などで知られており、長岡技術科学大や長岡造形大、長岡高専などが立地するなど教育環境も整ったこの地方の中核的な都市です。
同市では、総務省の「自治体戦略2040構想研究会」で掲げられた自治体職員が半減しても行政サービスを維持できる体制づくりを想定しながら、行政DXを推進しています。
今回は、その一環として業務の負荷が大きい心身の健康に関する相談業務に導入いただいた「AI相談パートナー」の導入経緯や効果について、お話を伺いました。

- 人口:25万5,539人
- 世帯数:11万461世帯
【課題】15名の保健師が年間約1,500件の相談業務に対応。相談業務以外の相談記録票の作成などに時間を取られ、過大な業務負担の改善が課題となっていた
Q.長岡市では、ICTの導入・活用やDXに対して、どのように取り組まれていますか?また「AI相談パートナー」の導入経緯について教えてください。

行政DX推進課 行政DX担当係長
栗山 潤様
栗山様:総務省は、2018年7月に「自治体戦略2040構想研究会」の第二次報告書の中で、従来の半分の職員でも自治体として本来担うべき機能が発揮できるような仕組みを構築する必要があると示しています。
職員が半分になっても行政サービスを維持・継続するためには、デジタル技術の活用が欠かせません。長岡市では10年先、15年先を見据え、あらゆる分野でDXを徹底的に進めています。
そのためにも、できるだけ早くから庁内にデジタル技術の活用を浸透させていくことが重要です。そこで、まずは職員に、さまざまなデジタルツールに実際に触れ、実務での活用イメージを膨らませてもらうため、2022年8月に15社のデジタルソリューション関連企業を集めた庁内展示会を開催しました。
この展示会で、「相談記録票」の作成や管理、情報共有など相談業務に関する事務に課題を感じていた健康増進課が「AI相談パートナー」に触れたことをきっかけに、導入検討をはじめました。
Q.「AI相談パートナー」導入前はどのように「相談記録票」を作成されていたのですか?
上石様:電話内容のメモをとり、それを見返しながら記録票を作成していたため、時間がかかっていました。
本来、相談記録票は相談を受けた直後に作成するのがベストです。しかし、さまざまな業務を抱えており、すぐに記録票の作成に着手できないこともあるため、実際の相談から記録票の完成までに間が空いてしまうことがありました。
【導入】「AI相談パートナー」は「LGWAN」「電話業務以外にも使える」という要件に合っていた
Q.予算取りなどは、どのように進められたのですか?
栗山様:展示会を実施した後、興味を示した課と協議を重ね、2023年度当初予算に健康増進課に導入するための予算を要求しました。デジ田交付金も活用しています。
「LGWAN( 総合行政ネットワーク)内で運用される」「対面や訪問など電話相談以外にも使える」などを要件に、提案を募りました。その結果アイネスさんを選定し、2023年7月から導入準備を行い、2023年11月に運用を開始しました。
導入は3ライセンスで、各保健師が使用する業務用PCとは別に専用のPCを3台置き、利用の際は移動して利用するという運用で始めました。
上石様:導入当初は席を移動して使わなければならないこともあり、保健師によって利用頻度はまちまちでした。新しいツールは使い慣れることで浸透していくものですが、全員がいつでも手軽に使えるような環境ではなかったと思います。
行政DX推進課のハンズオンサポートやアイネスさんのアンケートなどをきっかけとして各保健師に働きかけ、利用促進を図っていました。
【成果】記録が残ることで、相談内容に集中できるようになった。さらに、生成AIを活用した要約機能により、記録票作成までの時間が、以前より6~9割と大きく削減された

(左から)健康増進課 上石 寧々様、
廣井 ゆい様
Q.導入後の成果について教えてください。
上石様:相談の電話は、毎日かかってくるので、「AI相談パートナー」を毎日利用しています。導入前は、電話を取りながら手書きでメモを取り、後でメモを見返しながら記録票を作成していたため、時間がかかっていました。導入後は、メモを取らなくても記録が残るので、安心してより相談に集中できるようになりました。
「AI相談パートナー」で文字起こしされたデータをコピーし、必要な部分をWordに貼り付けて相談記録票を作成するというフローに変わり、心理的にも時間的にも負担が軽減されました。
また、「AI相談パートナー」には、モニタリング機能やチャット機能が搭載されています。これらを活用して、電話相談中に、ほかの保健師がモニタリング機能や直接画面をのぞき込んで相談内容を把握し、対応策をチャット機能やふせんを使って伝えるなど、デジタルでもアナログでもアドバイスができるようになりました。この結果、チームで対応できるようになり、自分1人だけで対応しなければならないという不安から解放されました。
廣井様:「AI相談パートナー」には、相談内容から「眠れない」「食欲がない」など、特定のキーワードを検知すると、対応方法や関連情報がポップアップされるガイダンス機能があります。この機能を活用することで、市民を電話口でお待たせせずに済むようになりました。以前なら、一度電話を保留にし、ファイリングされた紙資料で内容を調べてからお伝えすることが多く、どうしても時間がかかってしまっていたのです。
栗山様:モニタリング機能やガイダンス機能などが、ベテラン保健師のノウハウの継承、着任したばかりの職員の育成に役立ってくれていると思います。
上石様:また、訪問の時間がなかなか確保できないことが課題でした。保健師にとって、相談相手と直接会って話をする家庭訪問は、その人の生活状況を理解することができ、信頼関係も築ける重要な保健活動です。記録票の作成にかかる時間を短縮できた分、訪問に時間を使えるようになりました。
Q.新機能である生成AIによる要約機能もお使いいただいていますが、いかがでしょうか?
栗山様:健康増進課での運用を開始した2023年11月と前後して、アイネスさんから「AI相談パートナー」に生成AIを活用した要約機能の搭載を予定していると聞き、すぐに予算化しました。
長岡市では庁内のさまざまな事務でChatGPT等の生成AIを利用し、効果を確認していたので、テキストデータの要約で更なる業務効率化が果たせることは確信していました。2024年7月より、要約機能の利用を開始しています。
上石様:記録票の作成フローも、生成AI要約機能の導入後は、要約されたテキストデータをそのままWordに貼り、細かい誤変換や事実とは異なる内容などを修正していくだけになり、劇的に楽になりました。
相談内容をテキスト化できるだけでも助かるのですが、相談記録票作成には、必要な部分を手作業で抽出する必要がありました。要約機能を利用することで、「相談概要」「主訴」「家族の情報」など、項目ごとに整理して要約してくれるので、加筆修正だけで相談記録票が完成するようになりました。
もともと、相談記録票の作成時間は、30分の電話相談であれば、記録票の作成に30分から1時間程度かかっていました。生成AIによる要約機能導入後は、15分以下に短縮されました。
地域訪問時の相談内容も、ICレコーダーの録音データを帰庁後に「AI相談パートナー」にアップロードしておけば、翌朝までにテキスト化されるため、出勤後に要約機能を使用することで、相談記録票の完成までが格段に速く、楽になりました。
変換精度は、どうしても話者の発音や声量に依存します。しかし、相談者は心身の健康に問題を抱えているため、声が弱々しいことが多いのです。そこで、「こういうことですか?」と確認復唱することで、テキスト化されるよう工夫しています。
廣井様:相談が長時間にわたった場合でも、リアルタイムでテキスト化されるため、メモをすべてとる必要がなくなりました。さらに、要約機能で相談の概要をまとめてくれるため、相談に向き合うことができます。
上司への相談や、ほかの保健師への引き継ぎも楽になりました。
【展望】健康増進課だけでなく、他課、全庁へと活用を広げていきたい
Q.「AI相談パートナー」を活用した今後の展望について、教えてください。
栗山様:利用環境としては、要約機能の導入による利用増を想定し、ライセンス数を3から7へ増やしています。また、健康増進課では、専用PCでの運用から各保健師の業務用PCで利用する運用に変更し、より手軽に使えるように改善しました。
また、10月から、ひきこもり相談支援室での相談業務で利用を始めています。子ども・青少年相談センターでも、相談内容の録音の可否の様子を見ながら少しずつ試行を始める予定です。
相談業務への活用の応用としては、重層的支援体制の整備にも活用できれば良いと考えています。いわゆる「8050」やダブルケアなど複雑化・複合化した支援ニーズには、従来の縦割りの仕組みでは対応できません。ワンストップ窓口の支援や関係機関の連携・情報共有など、さまざまな活用ができるのではないかと期待を寄せています。
また、生成AIによる要約機能は、活用幅が広いため、全庁で会議の議事録作成に活用するなどの展開も考えています。今後、アイネスさんと相談しながらベストなかたちを探っていきたいと思います。
【お問い合せ先】
今回、ご紹介しましたアイネスの「AI相談パートナー」について、より詳しい内容をお知りになりたい方は、下記からお問い合わせください。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。