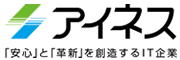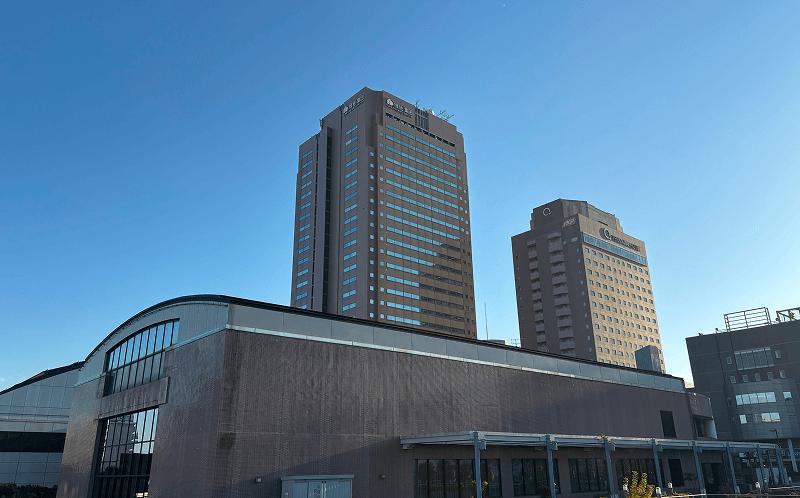【群馬県前橋市様】「タブレット訪問支援サービス」で生活保護業務の効率化を実現。

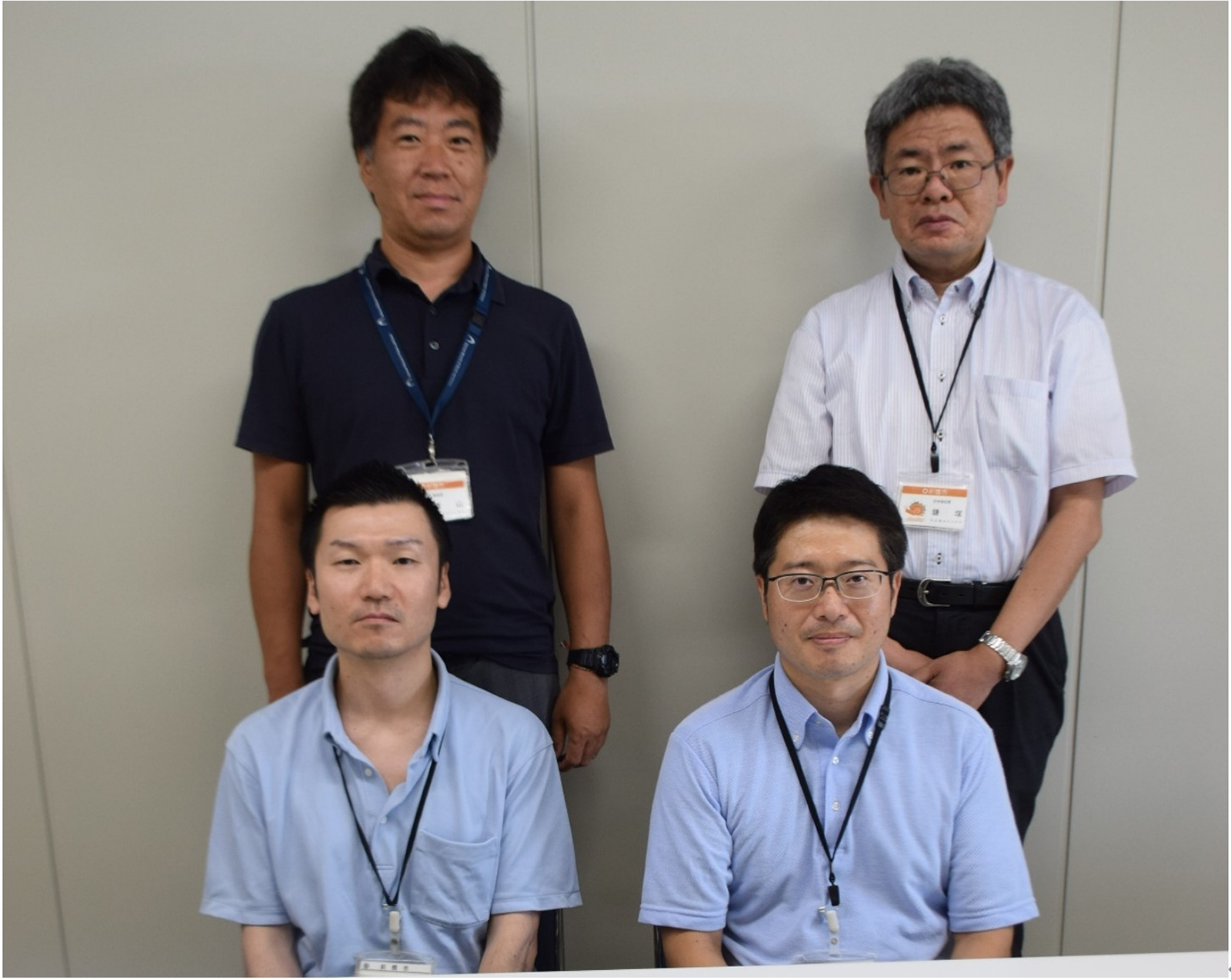
前列(右から)前橋市福祉部社会福祉課 副主幹 林 健太郎様、前橋市総務部職員課 主任 笠行 直生様 後列(右から)前橋市福祉部社会福祉課 副参事兼生活福祉係長 鎌塚博昭様 前橋市総務部職員課 課長補佐兼行政経営係長 横山茂之様
※笠行様、横山様は生活保護システム更新の時期、福祉部社会福祉課に在職されていました。
群馬県の中央部に位置する前橋市は、人口がおよそ32万8,000人。明治期に県庁が置かれ、群馬県政の中心地として機能してきました。
平成21(2009)年には、群馬県で初めて中核市に指定されました。それまで県が担っていた行政権限を委譲され、合わせて前橋市の行政機能の拡充が図られました。
前橋市では令和5(2023)年度、生活保護の業務システムを刷新し、アイネスの「WebRings(ウェブリングス)」を導入しました。
それとともに、生活保護業務にタブレット端末を活用する「タブレット訪問支援サービス」を導入し、ケースワーカーの仕事だけでなく、バックオフィスとなる社会福祉課の業務も大幅に改善されました。
そこで、これらサービスの導入経緯と導入後の効果についてお話をうかがいました。

- 人口:32万8,089人
- 世帯数:15万8,234世帯
- 生活保護受給世帯数:3,595人
- ケースワーカー数:41人
【課題】
生活保護のシステム刷新に合わせた業務効率化
前橋市は令和3(2021)年3月に「前橋市DX推進計画」を策定。住民サービスの向上を目的とした市役所の業務改善を進めるため、デジタル技術やデータ活用の推進を図ってきました。
生活保護業務を所管する福祉部社会福祉課では、ちょうど令和4(2022)年度に生活保護システムの更新時期を迎え、システムの一新と同時に、業務の見直しによる効率化を図ることが求められていました。
Q.システム刷新の時点で、生活保護の業務で直面していた課題を教えてください。
林様:仕事のほとんどが紙の書類と手作業なので、明らかに効率が悪いという問題がありました。現場に出ていくケースワーカーは、生活保護を受給している被保護者の方から挙証資料(生活の実態を示す書類)を提供していただくことがあります。被保護者のお宅を訪問した際に資料の原本をいったんお預かりして市の支所などに戻り、コピーしてから返還するという作業が必要で、被保護者のお宅を巡回する中で、そこに大きな時間がかかっていました。
ケースワーカーが被保護者の方から聞き取った情報の記録も、訪問後に手書きでメモをし、市役所に戻ってからパソコンで文書を作成し、印刷したものをファイルして部署内で共有するという手間をかけていましたので、書類の作成にかなりの時間を取られていました。
また、過去の記録や個々の被保護者に対する援助方針を記載した書類を庁外に持ち出すために、訪問時に確認する被保護者情報等を紙で印刷する作業も発生し、個人情報の取り扱いを慎重に行わなければならないといった場面もありました。
【導入】
セキュリティ部門と綿密に調整
Q.「タブレット訪問支援サービス」を導入いただくまでの経緯は、どのようなものでしたか?
林様:それまで利用していたシステムの保守が令和4年度末で終了し、新しいものに入れ替える必要がありました。紙の書類と手作業中心の状況を、システムの刷新に合わせて変えたかったということもありますが、少ない職員で効率よく事務を進めるためにも、タブレットを利用できるWebRingsを導入しようという考えになりました。WebRingsは令和5(2023)年4月に稼働、タブレットの利用は半年遅れて10月から始めました。
Q.以前のシステムでは、ケースワーカーの方が被保護世帯を訪問するときは、必要な情報をプリントやメモで持参していたということですが、タブレット訪問支援サービス導入によって、それがどのように変わったのでしょうか?
林様:生活保護システムから必要なデータを抜き出してタブレットにダウンロードし、訪問先に持参することができるようになりました。社会福祉課に配備された25台のタブレットを係ごとに割り当てています。ケースワーカーはタブレットを使う日をあらかじめ予約しておき、(被保護者世帯に)持参する前に生活保護システムにつないでデータを落とすという使い方です。
Q.持ち出すデータの中には、個人情報も含まれていますか。
笠行様:含まれています。そのため、タブレット訪問支援サービスの利用に当たっては、市の情報管理部門とかなり綿密な調整をしました。
Q.市のセキュリティポリシーの範囲内でタブレットを利用できるようにしたわけですね。
横山様:当時、社会福祉課に情報管理部門を経験した職員がいたので、セキュリティポリシーをきちんと理解した上で、こちらが何をしたいのかを正確に伝えることができました。担当課と情報管理部門の意思疎通ができていた点は大きかったと思います。
Q.タブレット自体にも、セキュリティ対策は講じていたのですね。
横山様:もちろん、パスワードをかけてありますし、一定の時間がたてば中のデータが自動的に削除されるMDM(モバイルデバイス管理)も設定しています。
Q.導入予算はどのように確保されたのでしょうか。
林様:タブレット訪問支援サービスはWebRingsと同時に調達していますので、予算もシステム移行とセットで確保しました。また、令和4(2022)年度の段階で厚生労働省が募集していた「生活保護業務デジタル化による効率手法開発・検証事業に係る生活困窮者就労準備支援事業費補助金」を申請し、補助金を受けることができました。
【成果】
ペーパーレス化で職場環境が激変
Q.タブレットを導入した効果を教えてください。
林様:システムへの情報入力が手作業だと月577.7時間かかっていましたが、タブレット利用によって192.5時間と385.2時間縮減できました。その結果、被保護者への訪問件数は月786件が1,186件へと400件増えました。また、訪問時に持参するために出力していた資料は、月6,000枚から0枚になりました。
Q.現場からの評価はいかがでしょうか。
林様:実際にタブレットを利用しているケースワーカーからは、訪問の準備が楽になったという声が大きいですね。以前は挙証資料をコピーして持ち帰る必要がありましたが、今はタブレットのカメラで撮影して、それをシステムにアップロードすれば作業は終わりなので、訪問後の作業もかなり効率化できています。
Q.WebRingsとタブレット訪問支援サービスの導入で、職場のペーパーレス化も進んだのでしょうか。
林様:生活保護システムへの情報入力から最後の決裁まで紙は必要なくなりました。もちろん、紙で受け取る書類もありますが、それもタブレットのカメラやスキャナーでデータ化して入力できるようになりました。その結果、書類がどんどん減って、今まで書類を保管していたスペースの削減にもつながっています。
鎌塚様:私は14年前まで社会福祉課にいて、この春の異動で戻ってきたのですが、以前は手書きのメモから始まって、手作業でファイルに文字を打ち込んで、それを印刷した書類で決裁を取るという流れでした。今はほとんどすべてがデジタル化されましたので、昔とは便利さが全然違うと感じています。
横山様:今のシステムが入るまで、どの机にも書類を入れるキャビネットが積み上がっていて、隣の同僚が席にいるのか、いないのかも分かりませんでした。当然、職場でのコミュニケーションもしづらい部分がありましたが、紙がないフラットな状態で仕事をすることで、その環境が大きく変わりました。
林様:システム導入に合わせて、社会福祉課の決裁の仕組みを見直しました。それまでは決裁が課長に集中していたのですが、SV(スーパーバイザー=係長)クラスの人でも決裁できる部分を切り分け分けました。ペーパーレス化で書類を回すこともなくなったので、事務の決裁までの時間がかなり早くなったと思います。
鎌塚様:係長で決裁できれば、課長の決裁までの時間がなくなります。そもそも、紙の書類を回していると、それを見るだけでも時間がかかります。その結果、組織としての意思決定も早くなったと思います。
【取材を終えて】
群馬県前橋市様は、タブレット訪問支援サービスを導入することで、目に見える形の成果を上げています。
最大の効果は、業務効率の大幅な向上です。導入前は紙と手作業が中心で、訪問準備や書類作成に膨大な時間を費やしていました。しかしタブレット活用により、訪問時の情報入力や証明書類のデータ化がその場で完結し、月385.2時間の業務時間削減に成功。これにより、被保護者への訪問件数を月400件も増加させることができました。
また、ペーパーレス化は職場環境も一変させました。書類の山が消え、物理的な見通しが良くなり、職員間のコミュニケーションも活発になりました。さらに、決裁プロセスの見直しも可能となり、組織としての意思決定が迅速化しました。
導入にあたってはセキュリティ部門と綿密に調整し、補助金も活用しています。業務効率化と住民サービス向上を両立させることで前橋市様のDX推進の確かな道しるべとなっております。
※ 本文に掲載されている会社名・団体名および製品名は各社または団体等の商標または登録商標です。